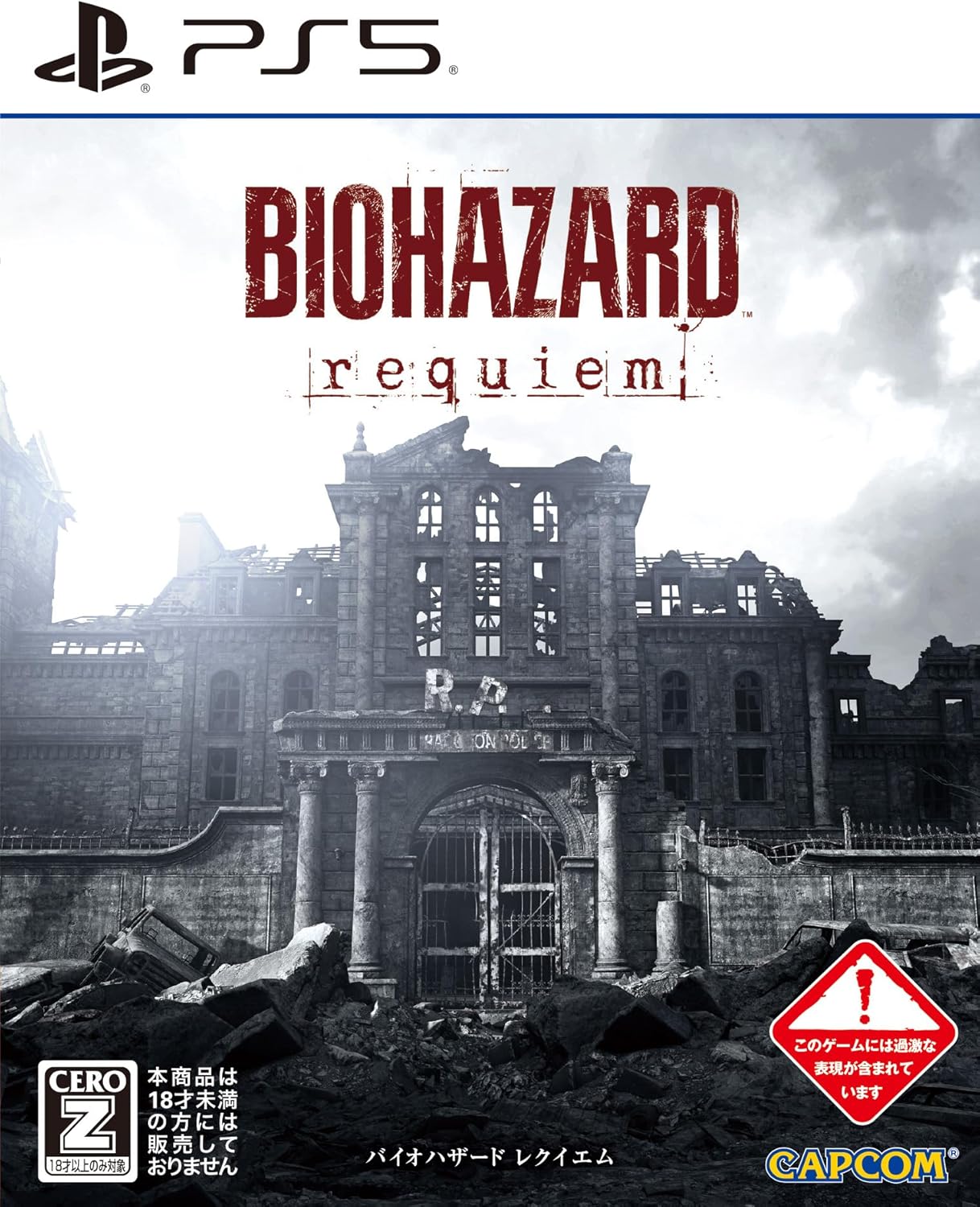PC-BSD FreeBSDをUSB-DVDからインストールしようとしたらエラーが出た備忘録
2014/03/02 Sun.
理由は特にないですが、FreeBSDが好きです。
先日のPuppyLinuxとは別のゲームマシンが、やはりXPのサポートが切れるということで、今回はFreeBSDディストリビューションの一つ、「PC-BSD」をインストールしようとしました。
すると、
Mounting from cd9660:/dev/iso9660/PCBSD_INSTALL failed with error 19.
というエラーで止まりました。
これを解決する備忘録。
先日のPuppyLinuxとは別のゲームマシンが、やはりXPのサポートが切れるということで、今回はFreeBSDディストリビューションの一つ、「PC-BSD」をインストールしようとしました。
すると、
Mounting from cd9660:/dev/iso9660/PCBSD_INSTALL failed with error 19.
というエラーで止まりました。
これを解決する備忘録。
category: パソコン
Puppy LinuxにGoogle Chromeをインストールする
2014/02/26 Wed.
ゲーム用パソコン(といってもFPSなどではなく、将棋やマージャンなどの軽いブラウザゲーム)のOSである「XP」のサポートがまもなく切れる。
たまにしか起動しない古いPCなので、新たにOSを購入するのは馬鹿らしい。
このままでもいいかと思ったが、PC-UNIX化することにした。
マシンはエプソンの「EDi Cube」。
PC-BSDやUbuntu、KNOPPIXを試したがインストールできない。
う~ん、困ったなあとネットを検索すると「Puppy」というLinuxを発見。
試してみるとあっさりとインストールできました。無線LANも音源も問題なし。ただ、使っていると時々画面に筋が入る。なんでだろう?
さて、このOSにはブラウザとして「オペラ」が入っています。
オペラでもいいのですが、Adobe FlashがLINUX版の対応を打ち切ってしまったので、OperaやFirefoxでは最新版のFlashを導入できない問題があります。
しかし、Google Chromeには標準でFlash機能がサポートされるとか言うことなので、導入することにしました。その備忘録。
たまにしか起動しない古いPCなので、新たにOSを購入するのは馬鹿らしい。
このままでもいいかと思ったが、PC-UNIX化することにした。
マシンはエプソンの「EDi Cube」。
PC-BSDやUbuntu、KNOPPIXを試したがインストールできない。
う~ん、困ったなあとネットを検索すると「Puppy」というLinuxを発見。
試してみるとあっさりとインストールできました。無線LANも音源も問題なし。ただ、使っていると時々画面に筋が入る。なんでだろう?
さて、このOSにはブラウザとして「オペラ」が入っています。
オペラでもいいのですが、Adobe FlashがLINUX版の対応を打ち切ってしまったので、OperaやFirefoxでは最新版のFlashを導入できない問題があります。
しかし、Google Chromeには標準でFlash機能がサポートされるとか言うことなので、導入することにしました。その備忘録。
category: パソコン
Avast antivirus と COMODO Firewall の組み合わせ
2014/01/24 Fri.
セキュリティー対策としてアバスト・アンチウィルスとコモド・ファイアーウォールを長年利用している。
理由は、どちらも無料だから。
そして、無料なのに有料ソフトに引けをとらない(いや、多くの有料ソフトより優秀だったりする・・・N○rt○nとか・・・)
ただ、ウィルス対策ソフトとファイヤーウォールが別々の製品の場合、不具合が発生することがある。
相性が悪いというか、似たような機能を両方が持っており、それがバッティングしたりすることがあるようだ。
今更ながら、この両者にもそういうのがあるらしいことを今日知った。
「サンドボックス」機能だ。
この機能を簡単に説明すると、素性のわからないプログラムをセキュリティーソフトが監視する隔離領域で実行し、疑わしい動きをしないか?を調べる機能です。
これは自動的に動きます。
ユーザーがソフトをインストールしようとしたときなどに、自動的に自分の監視下においてプログラムを実行。問題がなければインストールの続行を許す。
みたいな働きをします。
このサンドボックス機能、アバストにあるのは知っていましたし、実際に稼動して「ちょっとお待ちを」とインストールを待たされたことがある。
が、COMODOファイアーウォールにもあるとは知らなんだ。
つまり、素性のわからないプログラムの起動時に、それを奪い合い、予期しない動作を起こす可能性があるとのこと。
うーん。今まで特に何も感じなかったが、ネット上で片方だけにしたほうがいいような記述を見かけたのでそうすることにする。
ということで、COMODO Firewallのサンドボックス機能をオフにする備忘録です。
~オフの仕方~
COMODOのメイン画面を開き、右上の矢印マークをクリックして「Task」画面を開く。
「Firewall Tasks」をクリック。
「Open Advanced Setting」をクリック。
左欄の「Defence+」をクリックしてメニューを開く。
開いたメニューに「sandbox」があるのでそれをクリック。
「Enable automatic startup for services installed in the Sandbox」のチェックをはずす。
以上。
理由は、どちらも無料だから。
そして、無料なのに有料ソフトに引けをとらない(いや、多くの有料ソフトより優秀だったりする・・・N○rt○nとか・・・)
ただ、ウィルス対策ソフトとファイヤーウォールが別々の製品の場合、不具合が発生することがある。
相性が悪いというか、似たような機能を両方が持っており、それがバッティングしたりすることがあるようだ。
今更ながら、この両者にもそういうのがあるらしいことを今日知った。
「サンドボックス」機能だ。
この機能を簡単に説明すると、素性のわからないプログラムをセキュリティーソフトが監視する隔離領域で実行し、疑わしい動きをしないか?を調べる機能です。
これは自動的に動きます。
ユーザーがソフトをインストールしようとしたときなどに、自動的に自分の監視下においてプログラムを実行。問題がなければインストールの続行を許す。
みたいな働きをします。
このサンドボックス機能、アバストにあるのは知っていましたし、実際に稼動して「ちょっとお待ちを」とインストールを待たされたことがある。
が、COMODOファイアーウォールにもあるとは知らなんだ。
つまり、素性のわからないプログラムの起動時に、それを奪い合い、予期しない動作を起こす可能性があるとのこと。
うーん。今まで特に何も感じなかったが、ネット上で片方だけにしたほうがいいような記述を見かけたのでそうすることにする。
ということで、COMODO Firewallのサンドボックス機能をオフにする備忘録です。
~オフの仕方~
COMODOのメイン画面を開き、右上の矢印マークをクリックして「Task」画面を開く。
「Firewall Tasks」をクリック。
「Open Advanced Setting」をクリック。
左欄の「Defence+」をクリックしてメニューを開く。
開いたメニューに「sandbox」があるのでそれをクリック。
「Enable automatic startup for services installed in the Sandbox」のチェックをはずす。
以上。
category: パソコン
Windowsスクリプトでメール送信する方法
2013/07/18 Thu.
遠隔地にあるパソコンをWOLで起動するようにしているが、しばしば勝手に立ち上がっていることがある。
(´・ω・`)・ω・`) キャー
/ つ⊂ \ 怖いー
ということで、気がついたときに遠隔操作で電源を落とすのですが、立ち上がったことを知る方法がないかな?と考えた結果、ウィンドウズが立ち上がったときにメールを送ってくるようにすることに。
しかし、どうやって実現しよう。
と思ったら、ウィンドウズには便利なスクリプトが用意されていた。
Windows Script Host (ウインドウズ・スクリプト・ホスト)というやつです。
これの詳細はほかに譲るとして、これでメール送信をするサンプルを備忘録。
(´・ω・`)・ω・`) キャー
/ つ⊂ \ 怖いー
ということで、気がついたときに遠隔操作で電源を落とすのですが、立ち上がったことを知る方法がないかな?と考えた結果、ウィンドウズが立ち上がったときにメールを送ってくるようにすることに。
しかし、どうやって実現しよう。
と思ったら、ウィンドウズには便利なスクリプトが用意されていた。
Windows Script Host (ウインドウズ・スクリプト・ホスト)というやつです。
これの詳細はほかに譲るとして、これでメール送信をするサンプルを備忘録。
category: パソコン
東芝が世界最速のUHS-Ⅱ対応SDHCメモリカード「エクセリア」を出すみたい
2013/07/17 Wed.
東芝から高速書き込みができるSDHCメモリーカードが発売されるらしいのでメモ。
これで連射撮影が捗るな。
以下東芝サイトから抜粋。
--------------------
当社は、SDメモリカード規格Ver.4.10の高速シリアルバスインターフェース規格であるUHS-Ⅱ注1に対応し、世界最速の書き込み速度を実現したSDHCメモリカード「EXCERIA(エクセリア) PROTM」など2シリーズ4製品を、10月から順次発売します。
新製品は、「EXCERIA PROTM」、「EXCERIATM」の2シリーズで構成しており、より高速な転送規格UHS-Ⅱ対応に加え、当社独自開発のコントローラを搭載することで大幅に転送速度を高めています。「EXCERIA PROTM」は書込み速度が世界最速の240MB/秒で、UHS-Ⅰ対応の従来商品と比べて約2.5倍の速さを実現しています。これによりデジタルカメラの高速連写機能において書込み時間の長さによって発生するインターバル時間をより短くすることができ、一層細かい、連続性のある写真撮影が可能となります。
SDメモリカードの対応機器は多様化、高機能化しており、特にデジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラにおいては、高速連写機能使用時のインターバル時間や記録したデータのパソコン等へのコピー時間の短縮が求められています。また、フルHD動画の4倍の解像度である4K2K動画記録へのニーズが高まっており、大容量のデータをより高速に転送する機能が求められています。
1.UHS-Ⅱ対応「EXCERIA PRO」シリーズ
2.UHS-Ⅱ対応「EXCERIA」シリーズ
引用元東芝ニュースサイト
--------------------
この製品が出るころにはこの記事忘れてるんだろうな。
これで連射撮影が捗るな。
以下東芝サイトから抜粋。
--------------------
当社は、SDメモリカード規格Ver.4.10の高速シリアルバスインターフェース規格であるUHS-Ⅱ注1に対応し、世界最速の書き込み速度を実現したSDHCメモリカード「EXCERIA(エクセリア) PROTM」など2シリーズ4製品を、10月から順次発売します。
新製品は、「EXCERIA PROTM」、「EXCERIATM」の2シリーズで構成しており、より高速な転送規格UHS-Ⅱ対応に加え、当社独自開発のコントローラを搭載することで大幅に転送速度を高めています。「EXCERIA PROTM」は書込み速度が世界最速の240MB/秒で、UHS-Ⅰ対応の従来商品と比べて約2.5倍の速さを実現しています。これによりデジタルカメラの高速連写機能において書込み時間の長さによって発生するインターバル時間をより短くすることができ、一層細かい、連続性のある写真撮影が可能となります。
SDメモリカードの対応機器は多様化、高機能化しており、特にデジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラにおいては、高速連写機能使用時のインターバル時間や記録したデータのパソコン等へのコピー時間の短縮が求められています。また、フルHD動画の4倍の解像度である4K2K動画記録へのニーズが高まっており、大容量のデータをより高速に転送する機能が求められています。
1.UHS-Ⅱ対応「EXCERIA PRO」シリーズ
| 品番 | 容量 | 最大転送速度 | 価格 | 発売開始時期(予定) | |
| 読み出し | 書き込み | ||||
| THNSX016GAABM3 | 16GB | 260MB/秒 | 240MB/秒 | オープン | 2013年10月 |
| THNSX032GAABM4 | 32GB | 260MB/秒 | 240MB/秒 | オープン | 2013年10月 |
2.UHS-Ⅱ対応「EXCERIA」シリーズ
| 品番 | 容量 | 最大転送速度 | 価格 | 発売開始時期(予定) | |
| 読み出し | 書き込み | ||||
| THNSX032GAB4M3 | 32GB | 260MB/秒 | 120MB/秒 | オープン | 2013年11月 |
| THNSX064GAB4M4 | 64GB | 260MB/秒 | 120MB/秒 | オープン | 2013年11月 |
引用元東芝ニュースサイト
--------------------
この製品が出るころにはこの記事忘れてるんだろうな。
category: パソコン
EXCELで複数シートに一括設定を反映させる
2013/07/02 Tue.
エクセルでデータベースの仕様書をちまちまと作ってました。
テーブルをシートごとに分けて作成し、いざ印刷しようとプレビューを見てみたら、余白を設定し忘れていておかしなことになりました。
むーん。
「また一つずつ設定しないとダメなのか・・・」
はい、EXCELだいぶ長いこと使ってますが、今までこういう時、シート一つずつ同じ設定を行うか、マクロ組んで処理してました。
が、今頃になってようやく「これ一括設定できないの?」と疑問を持ったわけです。
文明の利器とは便利なのものです。一括設定できるんですね。
●やり方
一括設定したいシートを作業グループ化する。
全てのシートを設定したい場合、先頭のシート見出しをクリックし、シフトキーを押したまま最後のシート見出しをクリックするだけです。これでタイトルバーに[作業グループ]という表示が付きます。
この状態で
メニューの[ファイル]−[ページ設定]
で余白の調整をすると全てのシートに反映されます。
というか、
この状態でシートに文字を入力したり書式の設定を行うと、全てのシートに反映されます。
便利ですが注意も必要です。
作業グループを解除する方法は、作業グループになっていないシート見出しをクリックするか、シート見出しで右クリック[作業グループ解除]とやれば解除されます。
いやはや、マジで今頃気が付いたよ。これは便利だね。
しかし、私のオフィスは2003です。
古すぎます。
で、ちょっと調べたらすげー便利そうなフリーソフトを見つけました。
LibreOfficeです。
マイクロソフト・オフィスとの互換性もかなりあるみたい。
今度試してみます。


Microsoft Office Home and Business 2013
テーブルをシートごとに分けて作成し、いざ印刷しようとプレビューを見てみたら、余白を設定し忘れていておかしなことになりました。
むーん。
「また一つずつ設定しないとダメなのか・・・」
はい、EXCELだいぶ長いこと使ってますが、今までこういう時、シート一つずつ同じ設定を行うか、マクロ組んで処理してました。
が、今頃になってようやく「これ一括設定できないの?」と疑問を持ったわけです。
文明の利器とは便利なのものです。一括設定できるんですね。
●やり方
一括設定したいシートを作業グループ化する。
全てのシートを設定したい場合、先頭のシート見出しをクリックし、シフトキーを押したまま最後のシート見出しをクリックするだけです。これでタイトルバーに[作業グループ]という表示が付きます。
この状態で
メニューの[ファイル]−[ページ設定]
で余白の調整をすると全てのシートに反映されます。
というか、
この状態でシートに文字を入力したり書式の設定を行うと、全てのシートに反映されます。
便利ですが注意も必要です。
作業グループを解除する方法は、作業グループになっていないシート見出しをクリックするか、シート見出しで右クリック[作業グループ解除]とやれば解除されます。
いやはや、マジで今頃気が付いたよ。これは便利だね。
しかし、私のオフィスは2003です。
古すぎます。
で、ちょっと調べたらすげー便利そうなフリーソフトを見つけました。
LibreOfficeです。
マイクロソフト・オフィスとの互換性もかなりあるみたい。
今度試してみます。

Microsoft Office Home and Business 2013
category: パソコン
ディスク容量が足りなくてデフラグが動かない
2013/06/26 Wed.
パソコンが重い。
使っているパソコンはレッツノートCF-R3でOSはWINDOWS XP。
とっとと買い換えろ!と言う声も聞こえるが、バカにするなら金をくれ!である。
とりあえずデフラグをすることにする。
デフラグとは、細切れになったディスク上のファイルを整理整頓する作業のことです。
どういうことかというと、インストール直後のハードディスクはすっきりした空間が広がっています。
そこに、あんな画像やこんな動画を保存していく。見飽きたら削除する。
削除したところには空間ができるので、新しいファイルがそこに保存される。
しかし、サイズが違うので隙間ができたり、また逆に、そこに収まりきらず、残りを別の場所に保存されたりする。
それを長年繰り返しているうちに、一つのファイルが細切れになってディスク上に保存される状態になります。
そうなると、パソコンがファイルを読み書きする時間が遅くなるのです
で、それをすっきりさせるのが「デフラグ」と言う作業です。
WINDOWSには標準でデフラグがあります。
「プログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「デフラグ」
です。
「分析」を実行します。
ぐちゃぐちゃです。
デフラグを実行します。
「ハードディスクに空きがありません」みたいなことを言ってくる。
フリーのデフラグソフトを探す。
「Puran Defrag」というソフトを見つけました。インド産だそうです。
http://www.puransoftware.com/Puran-Defrag-Download.html
「0を発明した国の人だから、きっとすごいアルゴリズムなんだろう」
ということでインストール。起動。全部英語。
「デフラグぐらいThis is a penでいけるだろう」と思ったけどやっぱりよくわからない。日本語化します。
http://d.hatena.ne.jp/wwwcfe/20100206/purandefrag
上記から対応するパッチをダウンロードします。
展開すると32ビット、64ビットのファイルがありますので該当する方を「Puran Defrag」のインストールフォルダにコピーして、そのパッチを実行します。
それでPuran Defragを起動すると日本語になっています。
が、メッセージは英語のままだったりします。
単語を拾い読みしたところ、最初は再起動してデフラグ、そして、フルディスクチェックしなさいみたいなことらしい。
再起動デフラグは、通常動かせない領域もデフラグしてくれるようだ。
なので、ドライブを指定して、「ブートタイムデフラグ」ボタンをクリック。
一番下の「Restart-Defrag-Shutdown + Full Check Disk」を選んで実行しました。
おー、再起動がかかって何やら動き始めました。
・・・だいぶ時間がかかりそうなので散歩に行くことにしました。
40分ほど散歩して帰ってきたら終わってました。
電源ON。
無事起動。
体感的にはあまり変わらないなー。
やっぱり替え時なのだろうか。
使っているパソコンはレッツノートCF-R3でOSはWINDOWS XP。
とっとと買い換えろ!と言う声も聞こえるが、バカにするなら金をくれ!である。
とりあえずデフラグをすることにする。
デフラグとは、細切れになったディスク上のファイルを整理整頓する作業のことです。
どういうことかというと、インストール直後のハードディスクはすっきりした空間が広がっています。
そこに、あんな画像やこんな動画を保存していく。見飽きたら削除する。
削除したところには空間ができるので、新しいファイルがそこに保存される。
しかし、サイズが違うので隙間ができたり、また逆に、そこに収まりきらず、残りを別の場所に保存されたりする。
それを長年繰り返しているうちに、一つのファイルが細切れになってディスク上に保存される状態になります。
そうなると、パソコンがファイルを読み書きする時間が遅くなるのです
で、それをすっきりさせるのが「デフラグ」と言う作業です。
WINDOWSには標準でデフラグがあります。
「プログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「デフラグ」
です。
「分析」を実行します。
ぐちゃぐちゃです。
デフラグを実行します。
「ハードディスクに空きがありません」みたいなことを言ってくる。
フリーのデフラグソフトを探す。
「Puran Defrag」というソフトを見つけました。インド産だそうです。
http://www.puransoftware.com/Puran-Defrag-Download.html
「0を発明した国の人だから、きっとすごいアルゴリズムなんだろう」
ということでインストール。起動。全部英語。
「デフラグぐらいThis is a penでいけるだろう」と思ったけどやっぱりよくわからない。日本語化します。
http://d.hatena.ne.jp/wwwcfe/20100206/purandefrag
上記から対応するパッチをダウンロードします。
展開すると32ビット、64ビットのファイルがありますので該当する方を「Puran Defrag」のインストールフォルダにコピーして、そのパッチを実行します。
それでPuran Defragを起動すると日本語になっています。
が、メッセージは英語のままだったりします。
単語を拾い読みしたところ、最初は再起動してデフラグ、そして、フルディスクチェックしなさいみたいなことらしい。
再起動デフラグは、通常動かせない領域もデフラグしてくれるようだ。
なので、ドライブを指定して、「ブートタイムデフラグ」ボタンをクリック。
一番下の「Restart-Defrag-Shutdown + Full Check Disk」を選んで実行しました。
おー、再起動がかかって何やら動き始めました。
・・・だいぶ時間がかかりそうなので散歩に行くことにしました。
40分ほど散歩して帰ってきたら終わってました。
電源ON。
無事起動。
体感的にはあまり変わらないなー。
やっぱり替え時なのだろうか。
category: パソコン
動画ファイルの覚えたことをメモしておく備忘録
2013/06/12 Wed.
先ほど映像編集のことを書きましたが、今回「そーなのかー!」ということを覚えたのでメモしておく。
今回覚えた映像ファイルのこと
映像ファイルはコンテナとコーデックで形成される。
コンテナとはMOVやAVI、FLVなどのファイル形式で、動画コーデックはXvidやH264、VC-1など動画の圧縮形式。
つまり、動画コーデック、音声コーデックで圧縮したデータを収めたものがコンテナで、それが映像ファイル。普段「動画ファイルをくれ」といっているそれである。
そして、この映像ファイルを再生するときに問題になるのが、コンテナ(ファイル形式)に対応しているか?ということと、そのコンテナに収まっているコーデックがパソコンにインストールされているか?もしくは再生ソフトがコーデックを持っているか?ということ。
簡単に例えると、ネットで映画を買ったとして、
コンテナとはヤマト、ゆうぱっく、佐川で、
コーデックはVHS、DVD、ブルーレイディスク。
しかし、購入したお店によっては、ゆうぱっくのみ対応とか佐川は利用できないとか。
で、自分のデッキはVHSなのに見栄でBDを買っちゃったよ!再生できないよ!
みたいな理解でOK?
お店の部分の例えがおかしいかな?まあいいか。
今回は良くわからないままに高画質にこだわり「H264」を利用しましたが、この動画コーデックはWindowsXPにはインストールされていない。また、対応してないソフトもちょこちょこありそう。
そんなときは「Xvid」が良い感じ。
H264に一歩届かないが高画質という評判。しかも、このコーデックはフリーで開発されているとのこと。凄い人たちがいるもんだね。
自分のパソコンにどんなコーデックがインストールされているか確認する方法は、
「Windowsキー」を押しながら「Pauseキー」を押す。
「システムのプロパティ」が開くので「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」ボタンを押す。
「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ」を開いて、「ビデオCODEC」のプロパティを開く。
「ビデオCODECのプロパティ」の「プロパティ」タブを押す。
これで一覧が表示されます。
「Windowsキー」はキーボードの左下「Ctrl」の右隣のWindowsマークのキーですよ。
あ、それとこの説明はXPです。Windows8?なにそれ?
れれ?今一覧を見てみたら、このパソコンにはXvidも入ってないや。
動画編集に使ったPCには入ってたのになー。
動画関連のソフトを入れた時に入ったんだろうな。さすがフリーのコーデック!
ところで、みなさん再生ソフトは何使ってますか?
私は「VLC media player」の一択です。
とにかく内蔵コーデックが豊富!このソフトに内蔵しているのでパソコンにコーデックをインストールしなくても再生できます。
私のように映像ファイルのことよくわかってない人は、VLCをおすすめします。無料ですし。
今回覚えた映像ファイルのこと
映像ファイルはコンテナとコーデックで形成される。
コンテナとはMOVやAVI、FLVなどのファイル形式で、動画コーデックはXvidやH264、VC-1など動画の圧縮形式。
つまり、動画コーデック、音声コーデックで圧縮したデータを収めたものがコンテナで、それが映像ファイル。普段「動画ファイルをくれ」といっているそれである。
そして、この映像ファイルを再生するときに問題になるのが、コンテナ(ファイル形式)に対応しているか?ということと、そのコンテナに収まっているコーデックがパソコンにインストールされているか?もしくは再生ソフトがコーデックを持っているか?ということ。
簡単に例えると、ネットで映画を買ったとして、
コンテナとはヤマト、ゆうぱっく、佐川で、
コーデックはVHS、DVD、ブルーレイディスク。
しかし、購入したお店によっては、ゆうぱっくのみ対応とか佐川は利用できないとか。
で、自分のデッキはVHSなのに見栄でBDを買っちゃったよ!再生できないよ!
みたいな理解でOK?
お店の部分の例えがおかしいかな?まあいいか。
今回は良くわからないままに高画質にこだわり「H264」を利用しましたが、この動画コーデックはWindowsXPにはインストールされていない。また、対応してないソフトもちょこちょこありそう。
そんなときは「Xvid」が良い感じ。
H264に一歩届かないが高画質という評判。しかも、このコーデックはフリーで開発されているとのこと。凄い人たちがいるもんだね。
自分のパソコンにどんなコーデックがインストールされているか確認する方法は、
「Windowsキー」を押しながら「Pauseキー」を押す。
「システムのプロパティ」が開くので「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」ボタンを押す。
「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ」を開いて、「ビデオCODEC」のプロパティを開く。
「ビデオCODECのプロパティ」の「プロパティ」タブを押す。
これで一覧が表示されます。
「Windowsキー」はキーボードの左下「Ctrl」の右隣のWindowsマークのキーですよ。
あ、それとこの説明はXPです。Windows8?なにそれ?
れれ?今一覧を見てみたら、このパソコンにはXvidも入ってないや。
動画編集に使ったPCには入ってたのになー。
動画関連のソフトを入れた時に入ったんだろうな。さすがフリーのコーデック!
ところで、みなさん再生ソフトは何使ってますか?
私は「VLC media player」の一択です。
とにかく内蔵コーデックが豊富!このソフトに内蔵しているのでパソコンにコーデックをインストールしなくても再生できます。
私のように映像ファイルのことよくわかってない人は、VLCをおすすめします。無料ですし。
category: パソコン
MOV形式動画フィルをAVIに変換して音声を消去する備忘録
2013/06/12 Wed.
先日、初めてYouTubeに動画をアップロードしたのですが、動画編集に不慣れなもんでいろいろ試行錯誤したので次回のための備忘録兼作業記録。
といっても、やったことはあまりにも簡単。
撮影した映像の中の不要なシーンをカット。音声を削除しただけ。
これだけのことに色々悩んだ。
まずWindowsムービーメーカーを起動したが、デジカメの動画ファイルを読めない。
カメラのムービーファイル形式がMOV形式。こいつを読めないようだ。
WMVやAVIなら読めるみたい。
なので、MOV形式からそれらのファイルに変換するフリーソフトを探す。
見つけたソフトで変換したあとムービーメーカーで無事編集完了。保存もできた。
しかし、再生してみるとなんか映像が汚い。画質が悪いのです。
なんでも、ムービーメーカーではWMV形式でしか保存ができず、これでは残念画質になってしまうようだ。
※ちなみにいまだにXPです。VISTA以降は知らね。
というわけで、以下をキーワードにソフトを選んで作業をすることにします。
・簡単操作
・映像のカット、音の削除
・高画質
です。
ちなみにMOV形式は「QuickTime file format」のことなのでQuickTimeを導入すると簡単なのかもしれないが、昔QuickTimeを使った印象が悪かったので入れてないし今回入れる気もない。なのでQuickTimeに依存しないものを探す。
といっても、やったことはあまりにも簡単。
撮影した映像の中の不要なシーンをカット。音声を削除しただけ。
これだけのことに色々悩んだ。
まずWindowsムービーメーカーを起動したが、デジカメの動画ファイルを読めない。
カメラのムービーファイル形式がMOV形式。こいつを読めないようだ。
WMVやAVIなら読めるみたい。
なので、MOV形式からそれらのファイルに変換するフリーソフトを探す。
見つけたソフトで変換したあとムービーメーカーで無事編集完了。保存もできた。
しかし、再生してみるとなんか映像が汚い。画質が悪いのです。
なんでも、ムービーメーカーではWMV形式でしか保存ができず、これでは残念画質になってしまうようだ。
※ちなみにいまだにXPです。VISTA以降は知らね。
というわけで、以下をキーワードにソフトを選んで作業をすることにします。
・簡単操作
・映像のカット、音の削除
・高画質
です。
ちなみにMOV形式は「QuickTime file format」のことなのでQuickTimeを導入すると簡単なのかもしれないが、昔QuickTimeを使った印象が悪かったので入れてないし今回入れる気もない。なのでQuickTimeに依存しないものを探す。
category: パソコン
VAIOでWakeup On Lan機能を利用する
2012/09/05 Wed.
ひょんなことでVAIO「PCV-HS13BL5」という古い機種が手に入った。
何に使おうか?
手元にアナログTVチューナーボードがある。
ふと思いついた。
実家はケーブルテレビに加入している。
そのケーブルテレビにはアナログ信号のテレビが流れている。
それの録画機にしてしまおう。
というのも、実家に帰った時に、「時々(というかまれに)録画したいテレビがあるんだよなあ」と両親につぶやかれるときがある。
しかし、両親はびっくりするほどの機械音痴。
当然録画機など買わない。買ってあげない。使えないんだもん。
なので、このPCを録画機にして、こちらから遠隔操作で録画、再生してあげるというアイデアです。
しかし、まれな録画のためにこのPCを起動しっぱなしというのは電気代この節電が叫ばれるときに電気の無駄になる。
両親を電話で起動し、PCの電源を入れさせるという方法もあるのだが、これはちょっとナンセンス。というのも、往々にしてこちらの都合通りに動かない可能性が高い。
うーん・・・。
ずいぶん昔からその言葉だけは知っていた「Wakeup On LAN」とやら言うものを、今更ながら試してみようか。
というわけで、ようやく本題に入るのです。
が、続きは後日!
何に使おうか?
手元にアナログTVチューナーボードがある。
ふと思いついた。
実家はケーブルテレビに加入している。
そのケーブルテレビにはアナログ信号のテレビが流れている。
それの録画機にしてしまおう。
というのも、実家に帰った時に、「時々(というかまれに)録画したいテレビがあるんだよなあ」と両親につぶやかれるときがある。
しかし、両親はびっくりするほどの機械音痴。
当然録画機など買わない。買ってあげない。使えないんだもん。
なので、このPCを録画機にして、こちらから遠隔操作で録画、再生してあげるというアイデアです。
しかし、まれな録画のためにこのPCを起動しっぱなしというのは
両親を電話で起動し、PCの電源を入れさせるという方法もあるのだが、これはちょっとナンセンス。というのも、往々にしてこちらの都合通りに動かない可能性が高い。
うーん・・・。
ずいぶん昔からその言葉だけは知っていた「Wakeup On LAN」とやら言うものを、今更ながら試してみようか。
というわけで、ようやく本題に入るのです。
が、続きは後日!
category: パソコン